 [ 写真:永田さん ]
[ 写真:永田さん ]
神戸を拠点に防災・減災活動に取り組むNPO法人プラス・アーツ。プラス・アーツでは「防災の楽しさを世界中のみんなに」をテーマに、数多くの防災啓発イベントを企画しています。そんなプラス・アーツの理事長である、永田宏和さんにお話を伺いました。

 [ 写真:永田さん ]
[ 写真:永田さん ]
神戸を拠点に防災・減災活動に取り組むNPO法人プラス・アーツ。プラス・アーツでは「防災の楽しさを世界中のみんなに」をテーマに、数多くの防災啓発イベントを企画しています。そんなプラス・アーツの理事長である、永田宏和さんにお話を伺いました。
阪神・淡路大震災が発生した当時は何をされていましたか。
どうして防災啓発に関する活動をしようと思ったのですか。
永田さん:震災から10年の間に、ゼネコンを退職し自分で会社を興して、企画やまちづくりの仕事、アートや子ども向けのイベント等をしていました。震災当時のやるせない気持ちを引きずりながらも、どこかで記憶が薄れていくようなタイミングで、震災から10年目に防災啓発イベントを企画してほしいと声がかかったんです。その時にやっと自分の番が来たなと思いました。これまでのやるせなさを、この10年目に全てぶつけようと思いました。
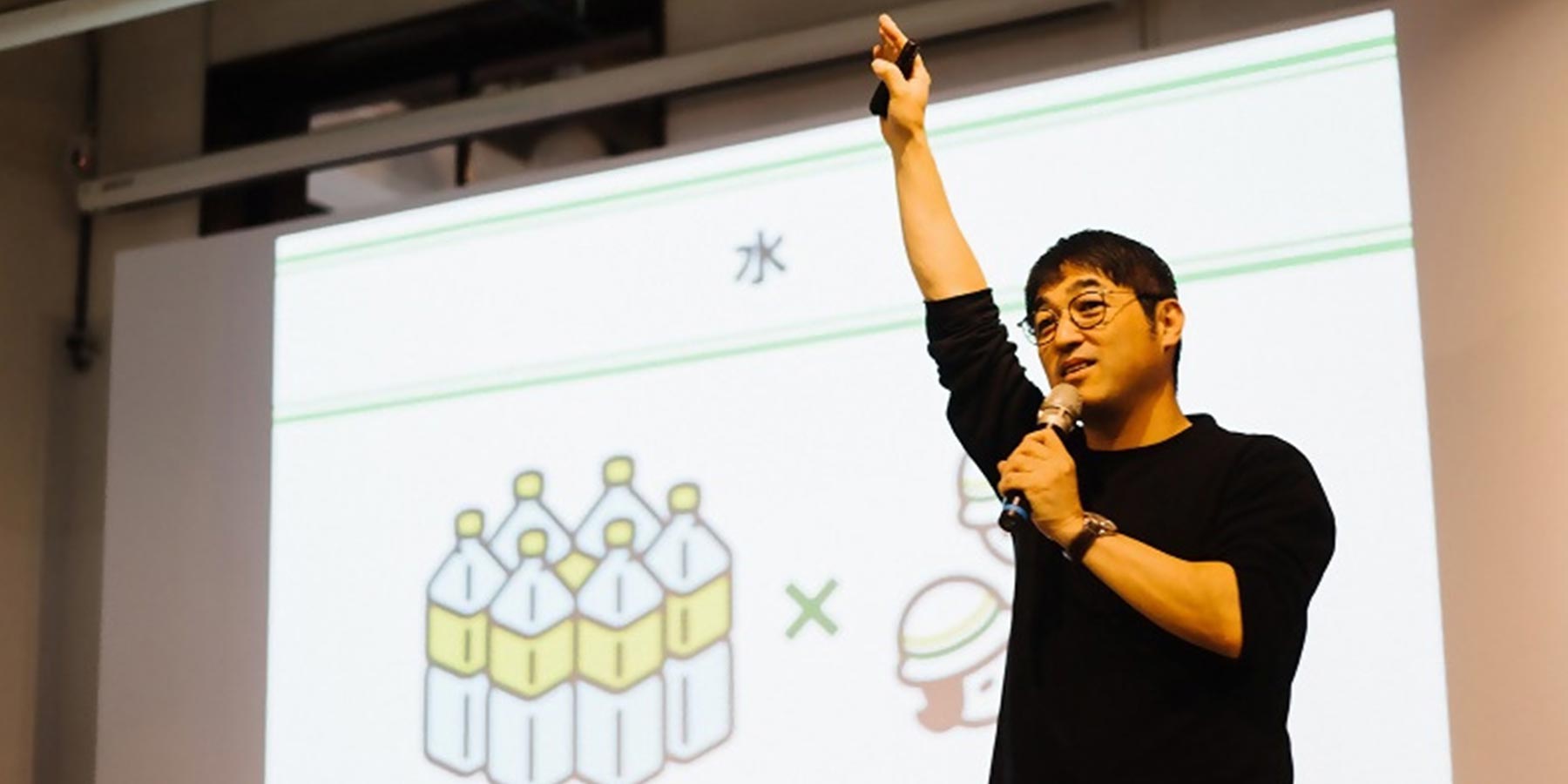
防災活動を始める際に気を付けていたことはありますか
永田さん:まず震災や防災について、リサーチを始めました。調べていると、震災から10年の間に、びっくりするくらい意識が風化していたように感じました。ハザードマップを配っても翌日には捨てられているとか、防災訓練に人が来ないとか。10年前に学んだことが風化している状況がありました。そもそも防災というテーマは伝えにくいもので、ハードルが高いのだと認識しました。その後に実施したのは、被災者へのインタビューです。本当に被災地で役に立つ知識は何なのか、それを知らないといけないと思いました。インタビューしたおじいちゃん、おばあちゃんからは、「お前に託すからがんばれよ」とも言われました。でも実際に伝える際にどうやって伝えれば良いのか、すごく大きなハードルだと感じ、防災だけを考えてもだめではないかと思ったんです。伝えたい相手が子どもだったら、子どもが何に興味を持っているのか、子ども向けのイベントではどのように集客しているのか等、そういうところに思考回路を持っていきました。そのような発想は、防災をやっていなかった自分だから持てたものだと思います。
防災を人に伝える際に意識していることはありますか。
永田さん:伝える方法はキャンプだったり、ゲームだったり何でも良いと僕は思います。ただ、伝える内容はしっかり考えないといけません。僕たちが大事にしているのは被災者の声を忘れないということです。被災者が本当のことを一番知っていますので。被災地で役に立つ知識や技は経験した人しかわからない。そういう人たちの話をとにかく聞いて学びました。情報収集をしっかりして、伝える内容は信頼できるものにする。伝える方法は若い皆さんの発想で柔軟に考えてくれたら良いと思います。僕が初めて防災啓発イベントに楽しめる要素を加えた時、すごくバッシングされましたが、伝えている内容は間違いないという自分の中での確信や自信を持っていました。真面目にやっても伝えたい人が来てくれないと伝えられませんので、伝え方の工夫が必要だと考えています。

現在の取組みに課題や悩みはありますか。
永田さん:課題はたくさんあると思っています。防災の知識や技を広めていくのは、結構ハードルも高く、そんなに簡単ではないんです。そのために、特に僕が重要だと考えているのは、防災教育の担い手を育てるということです。防災に関するプログラムを作ってほしいと依頼されたら作りますが、それを伝えていく担い手を育てていかないと多くの人を救うことはできないと思います。だから、僕は講演の依頼を受けたら断らないようにしているんです。なぜならその参加者の中にこれから担い手になる人がいるかもしれませんので。防災を伝えられる人材の育成が何よりも重要だと思っています。
震災を経験していない10代・20代へのメッセージをお願いします。
永田さん:震災を知らないから防災の担い手になれないかというと、そんなことはないです。私自身、もともと防災に関わってきたわけではない中で、アイデアを出し合いイベントを作ってきました。担い手は想いやモチベーションがあれば、誰でもなれます。ご高齢の方々が、体を張って防災活動や地域の活動を頑張っているのだから、若い世代にも地域や社会に関心を持って貢献してほしいですね。ただ、つまらなくて仰々しいものに無理やり取り組んでほしいわけではなくて、楽しく学べる等のモチベーションをもって取り組める場を僕ら世代が作っていきたいと思っています。そして、その場を支える10代・20代と、お互いに協力し合って取り組んでいけたら良いですね。期待しています。
永田さん:1995年の震災当時は都市開発の夢を抱いて、ゼネコンで働いていました。しかし、震災によって、開発どころか神戸のまちはズタズタに壊れてしまったんです。当時の私は京都のショッピングセンターの設計を担当しており、自宅があった大阪から神戸に背を向けて職場に通っていました。実家が西宮にあったのですが、そのあたりも被害が大きかったです。自分にはそれまで学んできた都市開発やまちづくりのノウハウ、地元への想いがありましたので、震災後すぐにでも西宮に飛んで行って、被災地の調査や復興業務に従事したいと思いました。当時の上司や上層部に、その旨を直談判しましたが、当然却下されました。いくら想いを語っても叶わないし、同じ想いを持っている人はたくさんいたと思います。結果的に僕は1995年には何もできていないんです。まちづくりや建築を勉強してきて、ふるさとは西宮のくせに何もできなかった。すごくやるせない気持ちが自分の中にありました。週末にはボランティアに行ったりもしましたが、週一回程度のボランティアでは役に立てているとは思えませんでした。